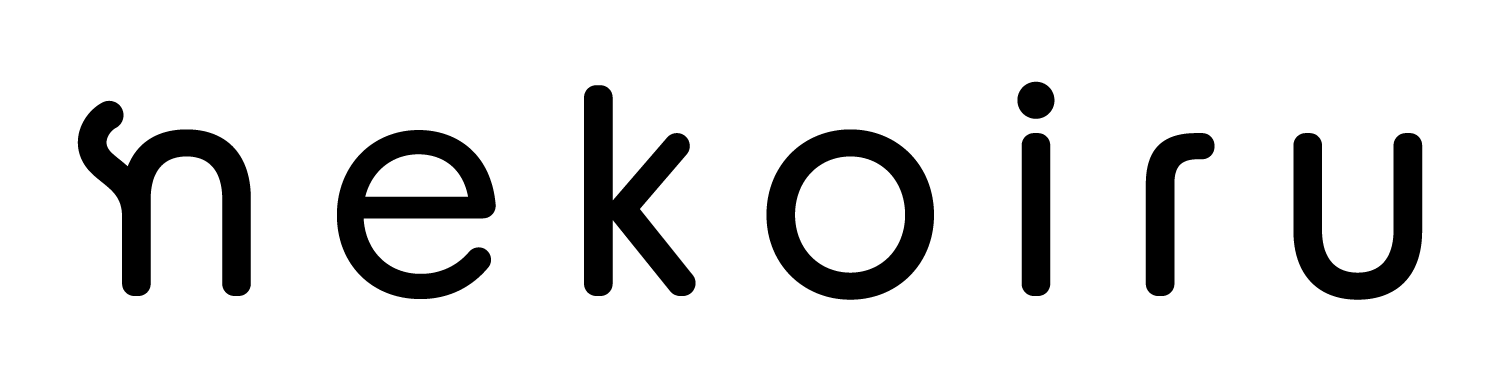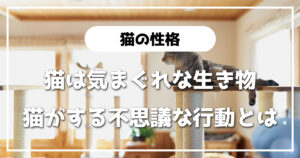猫は甘噛みする生き物

猫と過ごしていて、遊んでいるタイミングやなんでもないときに突然「ガブッ」と甘噛みされたことはないでしょうか?
じゃれている姿はとても可愛らしいですが、そのまま放置していると噛み癖がついてしまうことがあります。
大人になるにつれて噛む力も強くなっていくので、子猫の間に噛み癖を付けさせないようにすることが大切です。
猫に甘噛みをされる理由を飼い主さん自身が分からないと
- なんで噛むんだろう?
- やめさせるにはどうしたらいいんだろう?
- もしかして自分のことが嫌い…!?
と思ってしまいますよね。
実は、猫は「様々な理由」から甘噛みをします。
噛み癖をつけないためにもその理由をしっかり理解して、愛猫に寄り添ってあげることが必要不可欠です。
そこで今回は猫が甘噛みする7つの理由と、噛み癖を付けないための対処法について解説していきます。
この記事を読めば、猫が甘噛みしてきたときの猫の気持ちと「何をすべきか」がわかります。
猫の気持ちを知って、しっかりと対処してあげましょう!
 男性飼い主
男性飼い主猫の気持ちをもっと
人間が理解してあげよう。
猫が甘噛みしてくる7つの理由とは


猫はいったいどんなときに甘噛みをしてくるのでしょうか。
噛む理由を知ることで、飼い主さんがとるべき行動やしつけの方法も見えてきます。
ここでは猫が甘噛みする理由を7つ紹介していきます。
狩猟本能や遊びたい欲求
猫は動いているものを見ると本能的に追いかけたり噛みついてしまうことがあります。
猫は生まれたときからハンターなのです。
特に子猫の場合は何にでも興味を持つので、飼い主さんの足だろうと手だろうとそれが「獲物」だと思ったらじゃれついて甘噛みをしてきます。
猫はもともと狩猟動物なので狩りをしないとご飯が食べられず、生きていくことができません。
家で過ごしている猫は狩りをしなくてもごはんを食べることができますが、その狩猟本能は「遊び=狩り」としてずっと色濃く残っています。
本能的に備わっている欲求が満たされないとストレスが溜まってしまうので、普段からしっかり遊んで狩猟本能を満たしてあげるようにしましょう。
ただし、人間の手や指を使って遊ぶことは絶対にしてはいけません。
じゃれつく姿がかわいいからといって、手や指を使ってじゃれさせていると「人間の体は噛んでもいいおもちゃ」と覚えてしまいます。
噛み癖の原因になってしまうので「必ず」おもちゃなどを使って遊ぶようにしましょう。
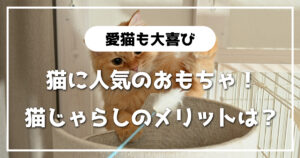
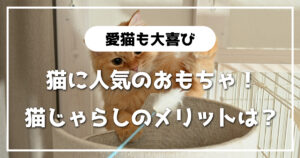
ストレスが溜まっている
猫はストレスを感じると、関係のない人や同居の猫を噛むことによって「ストレスを発散」させようとします。
これは猫の「転嫁行動」という習性によるもので、関係のない人や同居の猫に八つ当たりをすることにより気持ちを落ち着かせているのです。
人間もイライラしたときに物に当たったりすることがありますよね。
猫も同じように行き場のない思いを「何かを噛む」ことで発散させているのです。
生活環境が急に変わったり、お気に入りの場所が侵略されていたりすると猫はストレスを感じやすくなってしまいます。
ストレスが原因の場合はその理由を探して取り除いてあげることが大切です。
発情している
去勢をしていないオス猫の場合「発情期」を迎えると飼い主さんや家具に対して噛みつくことがあります。
オス猫は交尾のときに、メス猫の首を噛むことで体を抑え込もうとします。
その習性から飼い主さんの足などをメス猫に見立てて噛んでしまうことがあるようです。
また発情期は男性ホルモンの影響や、縄張り意識から飼い主さんや他の猫に対して「攻撃的」になりやすい時期でもあります。
本能による行動のためしつけでやめさせることは難しいですが「去勢手術」をすることによってほとんど収まっていきます。
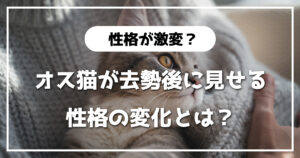
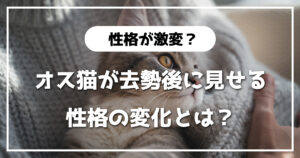
触るのをやめてほしい


猫を撫でているときにいきなり「ガブッ」と噛まれるのは「これ以上は触らないでほしい」という意思表示です。
「愛撫性誘発攻撃行動」と呼び、飼い主さんのスキンシップが長すぎたり撫でてほしくないところを触り続けていると猫は「やめて!」と甘噛みをしてきます。
飼い主さんとしては「気持ちよさそうにゴロゴロいってくれていたのになぜ?」と思ってしまいますよね。
実はよく見ると猫は噛む前にイライラのサインを出しています。
撫でているときに猫が噛んでしまうのは我慢の限界に達した時なのです。
耳を横に倒す「イカ耳」になったり、しっぽを「バタバタ」させていると、猫がイライラしている証拠。
イライラのサインを見つけたら少し名残惜しいですが触るのをやめてあげましょう。



怒ってる猫も可愛いけど
触るのを我慢してあげよう。
病気やケガをしている
今までは全然噛んでくることがなかったのに、突然噛むようになったという場合は病気やケガが理由の可能性があるので注意が必要です。
体のどこかに痛い場所がある場合「痛いところを触らないで欲しい」という要求から飼い主さんを噛む場合があります。
また「甲状腺機能亢進症」などの病気によってイライラしやすくなると、怒りっぽくなって噛んでしまうこともあるようです。
「猫が急に噛んでくるようになった」と感じた場合は、早めに病院への受診を検討しましょう。
https://www.jbvp.org/family/cat/metabolism/01.html
かまってほしい
飼い主さんが他のことに夢中で、あまりにも猫を相手にしてあげないと「かまって~!」と噛んでくることがあります。
- 遊んでもらえない
- ご飯がもらえない
と猫が感じると気を引くために噛んでアピールするようです。
普段から猫と触れ合う時間を作ってあげて、アピールされる前に気持ちを満たしてあげましょう。
歯がムズムズしている
子猫の場合、歯が生え変わる時期に噛んでくることがあるようです。
生後3ヶ月から6ヶ月に歯の生え変わりが始まると、子猫は口のなかに「ムズムズ」とした違和感を感じるようになります。
その違和感を解消するために、噛みたくなってしまうようです。
噛んでも壊れないような頑丈なおもちゃを用意してあげて、歯がゆさを解消させてあげましょう。
- 狩猟本能や遊びたい欲求
- ストレスが溜まっている
- 発情している
- 触るのをやめてほしい
- 病気やケガをしている
- かまってほしい
- 歯がムズムズしている
猫に噛まれた後のしつけ方法


ここまで甘噛みをされる理由について解説してきましたが、実際に噛まれた時はどのような対処をしていけばよいのでしょうか。
甘噛みをそのままにしておくと噛み癖がつきやすいですし、大人になるにつれてどんどん噛む力も強くなるので飼い主さんにとっても危険です。
噛み癖を付けないためにはその後の「しつけ」が重要になってきます。
ここからは噛まれた後のしつけ方法について解説していきます。
要求に応えない
猫に噛まれた時は基本的にはできる限り反応せず「無視」するようにしましょう。
噛んでくる原因がご飯や遊びの要求だった場合、そのたびに要求に応えていると
- 噛んだらごはんをくれる
- 噛んだら遊んでくれる
と覚えてしまいます。
猫は頭がいいので、一度覚えてしまうと要求があるたびに噛むようになるのです。
愛猫のお願いを飼い主としては「しょうがないな」と思って実行に移してしまうところですがここはぐっと我慢。
噛んで来た時にはサッと手を引くか反応しないようにして、できるだけ無視するようにしましょう。
すごく痛いかもしれませんが、あまり大げさにリアクションをとってしまうと「反応してくれた!」とかえって甘噛みを助長させる原因になります。
猫にとって噛んでもいいことがないと思ってもらうことが大切です。
興奮状態ではやめさせることを優先する
噛まれた時は手を引いて無視するのがよいのですが、興奮している時にはかえって「逆効果」になる可能性があります。
興奮しているときに手を引いてしまうと狩猟本能が刺激されて余計にヒートアップしてしまう場合もあります。
興奮している分、噛む力も本気になっている可能性があるため注意が必要です。
特に遊んでいる最中は猫もかなり興奮していることが多いので「痛い!」など短い言葉で声かけをして中断するのが良いでしょう。
噛んだまま離してくれないときには無理して手を引かず、逆に手を押し込むようにすると苦しくなって離してくれます。
噛むのをやめさせた後はできるだけ反応しないようにし、気持ちを落ち着かせてあげましょう。
怒ったり叱ったりは逆効果
猫は基本的に、噛んで怒られたとしても「なぜ怒られているのか」を理解することができません。
甘噛みしてきても猫に対して「怒る」「叩く」といった行動でしつけようとするのは絶対にやめましょう。
飼い主さんが噛まれたからと言って大きな声で叱っても「なんか大きい声を出してきた」と思うだけのことが多いようです。
大きい声を出すことで「反応してくれた!」とかえって嬉しくなってしてしまう場合もあります。
また「噛まれたら霧吹きで水をかける」というしつけ方法もありますが、これも「イヤなことがあった」と思われるだけで根本的な解決方法にはなりません。
大好きな猫にわざわざイヤな思いをさせて、嫌われたくはないですよね。
猫を怒ったり叩いたりすることは信頼関係が崩れてしまうだけでなく、ストレスを溜めて問題行動に繋がってしまう可能性もあるので絶対にやめましょう。
- 要求に応えない
- 興奮状態ではやめさせることを優先する
- 怒ったり叱ったりは逆効果
まとめ
猫の甘噛みをしつけるためには、その理由を飼い主さんが理解してあげる必要があります。
猫が甘噛みする理由には様々な理由がありますが、決して飼い主さんのことが嫌いだからではありません。
一緒に過ごす家族だからこそ気持ちを伝えてくれているのです。
狩猟本能や甘えたい気持ち、イヤな気持ちなどの理由をしっかり見極めて猫が噛まなくても幸せに過ごせる環境作りをしていきましょう。



猫と人間どちらも暮らしやすい
関係性を構築しましょう!